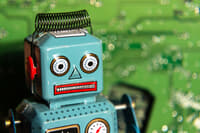中国版『ランボー』は(ある意味)本家を超えた

ド派手な戦闘シーンが続く『戦狼2』に映画的な深みはない Wolf Warrior 2-Official Trailer-YOUTUBE
<中国で大ヒットのアクション映画『戦狼2』が、あり得ない設定で描き出す「等身大の中国」>
中国映画といえば、社会問題や歴史を扱った芸術肌の監督による重厚な作品というのが世界の共通認識だった。張芸謀(チャン・イーモウ)の『紅いコーリャン』、あるいは賈樟柯(ジャ・ジャンクー)の『プラットホーム』といった名作が各国の映画賞を次々と獲得。そこに描かれる中国は嘘や偽りのない「等身大の中国」で、だからこそ世界の映画ファンに愛された。
しかし、最近中国国内で公開され、ヒットする中国映画はかなり違う。7月27日に公開された戦争アクション映画『戦狼2』は、その代表といっていい。
中国版『ランボー』と呼ばれる『戦狼2』は、人民解放軍特殊部隊に所属していた元兵士が、アフリカの架空の国で武装勢力や外国人傭兵部隊に襲われた自国民を救い出すストーリーだ。15年に製作された第1作に続く続編で、国境地帯での犯罪組織との戦いを題材にした第1作にも増して「現代中国の国情」を感じさせるつくりになっている。
【参考記事】「雨傘」を吹き飛ばした中国共産党の計算高さ
とにかく強調されるのが、アフリカと中国の友情だ。広域経済圏構想「一帯一路」の重要な目的地であり、急増する中国の投資を考えれば、アフリカ諸国が中国に対して好印象を持つのは当然だろう。欧米や日本には中国の新植民地主義がアフリカで嫌われているという思い込みがあるが、アフリカには「中国製でもインフラがないよりまし」という意識とともに、中国への親近感が広がっている。
ただ、この映画が描く「アフリカの中国愛」は度を越している。その最たるものが、主人公の元兵士が中国国旗を掲げた途端、戦火を交える武装勢力同士が戦闘をやめ、避難する中国人たちの乗った車列を無事通す、というラストシーンだ。12年にはザンビアの鉱山で、昨年はケニアの鉄道建設現場で現地労働者が中国人幹部を襲う事件が起きている。映画史に残る迷ラストシーンかもしれない。
主演のアクションスター呉京(ウー・チン)のマッチョぶりが「本家」シルベスター・スタローンに遠く及ばないのは、まだアメリカに及ばない国力を自覚した控えめさの表現だろう。それでも、映画には随所に白人コンプレックスと見受けられる場面が散在する。