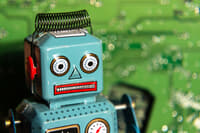マクロンは「朝貢」訪中で、人権にも触れず馬脚を現した

北京の美術館を訪問したマクロン大統領(1月9日) REUTERS
<中国マネーの前に去勢馬のように手なずけられた? 習近平の父祖の地に駆け付けたフランス大統領の思惑とは>
馬克龍――。「龍に克つ馬」という、内陸アジアのモンゴル人やチベット人、トルコ系カザフ人などが喜んで付けそうな格好いい名前である。
だが、この名を冠した人物は遊牧民ではなく、フランスのマクロン大統領だ。もっともこの漢字名を授けたのは彼の両親ではなく中国人。欧米の政治家にいかにも中国人らしい音を当てただけだ。
ちなみにトランプ米大統領に関しては、中国は「特朗普」と呼ぶのに対し、台湾は「川普」と表記。両者に「統一」する意思はないらしい。
「馬克龍」については中台が足並みをそろえたものの、音を当てることに夢中なあまり、中国のシンボルの龍が負けることには思いが至らなかったようだ。
1月8日から3日間にわたって中国を訪問したマクロンは滞在中、ずっと自分らしさを崩さなかった。彼は首都の北京ではなく、陝西省の省都・西安を最初の訪問地として選んだ。西安は古都長安から発展しており、共産主義の今の中国よりも古きよき中国のほうが好きだ、というシグナルを送ったとの解釈も見られた。
一方、陝西省は習近平国家主席の父祖の地でもある。大国フランスの大統領が「朝貢」に訪れたことを「習家の故郷に花を添える行為」として宣伝したい北京の思惑が働いたとも報じられている。果たしてマクロンの真意はどこにあるのだろうか。
西安城内に入るや否や、マクロンが真っ先に視察したのは中国側が準備した秦の始皇帝の兵馬俑ではなく、回民街だった。回民(回族)とはイスラム教を信奉し、中国語を母語とする人々を指す。長安の回民は唐時代にアラビアやペルシャから移住した人々の子孫ともいわれる。自国に多数のイスラム教徒を抱える大統領だからこそ、その生活実態をこの目で見るのも理にかなったことだろう。
200億ドル契約の土産
マクロンは明らかに「馬克龍」という中国名を気に入っており、おそらくその漢字の意味まで理解していたようだ。西安から北京に移動した後、早速、自身の名前にふさわしい外交を展開。「馬は龍に克つ」といわんばかりに習に馬を1頭プレゼントして、パンダ外交ならぬ「馬外交」を実践した。
これに対し、習側も苦笑いしながらその「朝貢品」を納めるしかなかった。というのも、「馬克龍」は去勢した馬を運んできたからだ。
旧植民地の心の傷に思いを馳せない日本の出版社 2023.11.04
777年前に招待状を出したモンゴルを、ローマ教皇が訪問する本当の狙い 2023.08.26
「チンギス・ハーンの子孫の国」へも越境法執行を始めた中国警察 2023.05.18
上海で拘束された台湾「八旗文化」編集長、何が中国を刺激したのか? 2023.05.01
中国による台湾言論界の弾圧が始まった 2023.04.21
ウクライナ戦争は欧米と日本の「反ロ親中」思想が招いた 2022.03.16