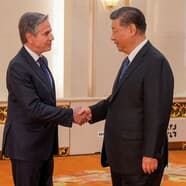ダイアナを「殺した」のはマスコミか
アメリカ在住のパパラッツィ、ラッセル・チューリアックも同意見だ。「人は有名人の写真を見たがる。だからこういう商売がある」
ビジネスの原則も変わりそうにない。フォトジャーナリズムの世界では、刺激的な写真ほど高く売れる。大金を手にしたいなら、ただの「有名人の写真」ではなく「有名人が何か刺激的なことをしている写真」でなくてはならない。
カメラマンが被写体の怒りを買う事例が絶えないのは、これが一因でもある。昨年ダイアナが二人の息子を連れてスイスにスキー旅行に行った際、一家はカメラマンの一団に取り囲まれた。家族のささやかなプライバシーを認めてほしい、とダイアナが頼むと、ほとんどのカメラマンはその願いを尊重したが、一人だけは撮影を続けた。当然のように、彼の撮った写真はあらゆるメディアで繰り返し使われた。
今年5月、アーノルド・シュワルツェネッガーと妻のマリア・シュライバーは、息子の通う学校の近くで車を走らせていた。学校まで約400メートルほどのところまで来たとき、カメラマンの乗った二台の車が彼らの前に割り込み、写真を撮りはじめた。
【参考記事】現代女性も憧れる「ダイアナヘア」はこうして生まれた
タブロイド文化は不滅
カメラマンたちはそれだけでは飽き足りず、夫妻が学校に着いてからもシャッターを押し続け、騒ぎを収拾しようとした校長を突き倒した(彼らは後に逮捕され、起訴されている)。
トム・クルーズは、ダイアナが死亡したパリのトンネルで自分もパパラッツィに追跡されたことがある、とCNNに語った。マイク・タイソンは本誌の取材にこう答えた。「自宅の庭の木陰に、奴らが隠れていたこともある。今度の事件はいい教訓になるはずだ」
そう期待していいものか。被写体とのトラブルでたたかれたケースは過去にも何度かあるが、タブロイド文化は不滅だった。今回の事故の直後でさえ、ダイアナの車をバイクで追いかけていたパパラッツィは、シャッターを押すのをやめなかった。これほどの大事件にさえタブロイド文化はびくともしない、という証明かもしれない。
パパラッツィの元締め的な存在の一人、マッシモ・セスティーニは、オートバイやヘリの調達など、パパラッツィたちが必要とするさまざまな「経費」を提供している。あの運命の晩、ダイアナを追っていた連中のなかに自分の配下もいた、とセスティーニは言う。
「彼はすべてを撮っている。衝突の瞬間、その後の現場風景、そしてダイアナの無残な写真も」。死体の写真は売らない、と彼は言った。だがどこかの誰かがそれを紙面に載せたいとか、手に入れたいと思わない保証はない。
【お知らせ】ニューズウィーク日本版メルマガリニューアル!
ご登録(無料)はこちらから=>>