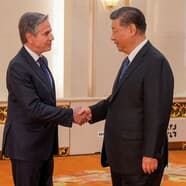トランプの訪欧に大逆風、前例のない抗議と不人気
調査機関ピュー・グローバル・リサーチが先週発表した調査結果によると、トランプの国際的なリーダーシップと政策に対して、国際世論の75%がほとんど、ないしはまったく信頼感を抱いていない。
多くの国々でトランプの支持率は2004年時点のブッシュ(息子)よりも低かった。予想どおりイスラエルとロシアではトランプの評価は高いが、この2国は例外的で、アジア太平洋諸国から南北アメリカ大陸まで、ほぼ世界中がトランプにノーを突きつけている。
【参考記事】トランプ、抗議デモ避けてイギリスに「密入国」?
【参考記事】トランプ「異例の招待」に英国民猛反発でエリザベス女王の戸惑い
先週のピュー・リサーチ・センターの調査結果が明らかにしたように、ブッシュ元大統領以降で初めて反米感情が多くの国で急増したことから、トランプは現代史で最も海外で不人気のアメリカ大統領になる可能性が出てきた。
それにより、バラク・オバマ前米大統領がアメリカのイメージを変えようとした8年にわたる努力のほとんどが無駄になるかもしれない。
オバマが2009年に大統領になって直面したのは、ベトナム戦争以来の最悪レベルにあった反米感情だ。その主な原因は、「テロとの戦い」と称したブッシュ政権の外交政策が、国際的に評判が悪かったからだ。
オバマが上げたアメリカのブランド価値
オバマ前政権は反米感情を逆転させるために様々な手を打った。ある研究によれば、オバマ前政権1年目だけで、「オバマ効果」はアメリカのブランド価値を2兆1000億ドルも押し上げた。ブッシュから政権を引き継いだ後、アメリカを世界で最も素晴らしい国とみなす外国人がかなりの割合が増加したことを示している。
国際社会でアメリカのイメージが改善したことを、米政府のみならず米企業も歓迎した。アメリカに本社を置く多国籍企業は、ブッシュ政権になってから海外ビジネスで反発を受けるなど、反米主義のはけ口になる懸念も生じていたからだ。
オバマは数々の成功を収めたが、成果は偏っていた。恐らくオバマの世界的なパブリック・ディプロマシー(大衆外交)における最大の失敗は、イスラム世界への対応だろう。
例えば、オバマは1期目にエジプトの首都カイロで有名な演説をし、イスラム教が多数派を占める国々との関係を修復すると約束したが、パキスタンやエジプトなどのイスラム同盟国でさえ、今も反米主義が根強く残っている。
それでもオバマ前政権末期に彼の国際問題に関する指導力を信頼すると回答した人の割合は、全世界で64%に上った。今のトランプをはるかに上回る数字だ。