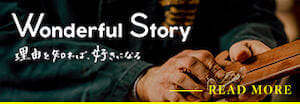- HOME
- コラム
- サイエンス・ナビゲーター
- 昆虫界でも「イクメン」はモテる! アピールのために…
昆虫界でも「イクメン」はモテる! アピールのために「赤の他人の卵」の世話すらいとわず
コオイムシの最大の特徴は、漢字表記の「子負虫」が示すように、メスがオスの背部に卵を産み、産み付けられたオスが卵を保護(子育て)しながら生活する習性を持つことです。コオイムシのオスは卵を産み付けられると飛ぶことができなくなり、敵に捕まる可能性が高まってしまいます。しかも、メスは子育てには全く協力してくれません。それにもかかわらず、卵が孵化するまでの間、オス単独でせっせと育児を行います。
近縁種のタガメもオスが子育てすることが知られていますが、あくまで稲などに産み付けられた卵塊を乾燥や外敵から守る役割です。タガメと比べると、コオイムシのオスの「イクメン」ぶりは、非常に献身的に見えます。
生物界における「父育」のリスク
生物は、子の生存率を高めて自らの遺伝情報を次世代につなぐために様々な戦略を取っています。なかでも「親による子育て」は、外敵から守ったり栄養を与えたりするのに有効な手段です。哺乳類ではメスによる子育てが一般的ですが、鳥類や魚類、一部の昆虫類、両生類などではオスが単独で子育てを行う「父育(Paternal care)」という行動も見られます。
一方、子育ては親にとって大きな負担となります。子のための余剰な餌を採取する必要があったり、子がいるために自分が外敵から逃げ遅れるリスクが高まったりするからです。そのため、生物界でオスが育児に参加する場合は「本当に自分の子である」という確信を持てる状況でのみ行われているという考えがこれまでの定説でした。
例えば、過酷な南極に住むコウテイペンギンは一夫一妻制で、交尾後に1つだけ卵を授かります。出産を終えて体力回復のために餌の魚を求めて海に向かうメスに代わって、オスはメスが戻って来るまでの約2カ月間、必死に卵を温めます。
タツノオトシゴは、オスの体内の育児嚢にメスが産卵し、育児嚢内で受精します。出産もオスの仕事ですが、タツノオトシゴのオスは100%自分が父親である子を育てており「托卵(他のオスの子を育てさせられている)」の心配はありません。
「モテるための条件」としての子育て
ところが、最近は「オスは自分の子だという確信が必ずしも高くなくても、イクメンアピール自体にメリットがある」可能性が報告されるようになってきました。たとえば、クモのような8本足を持つザトウムシの1種には、「オスが卵を保護しているという状況」自体が、メスから交配相手として選ばれやすくなる条件になっているという報告もあります。このような生物では、「モテるための条件」を満たすために、赤の他人の子(自分の子ではない卵)の世話をする可能性があるかもしれません。
「この名前を与えてもらって感謝」油井亀美也宇宙飛行士に聞いた、「亀」の支えと利他の原点 2025.06.10
-
「大手外資食品企業」Strategic Product Management
カーギルジャパン合同会社
- 東京都
- 年収900万円~1,100万円
- 正社員
-
プロダクトエンジニア「ポテンシャル採用/大手や外資系など3000社に導入/HR SaaS「ミキワメ」/東京都/港区虎ノ門/web系SE・PG
株式会社リーディングマーク
- 東京都
- 年収400万円~550万円
- 正社員
-
外資系メーカーの法人営業 年間休日127日/2年目以降、大幅昇給のチャンスも
ハイウィン株式会社
- 東京都
- 月給30万円~
- 正社員
-
事務 服装自由/土日祝休み 大手外資系アパレルメーカーの事務
株式会社Shigolabo
- 東京都
- 月給24万円~30万円
- 正社員