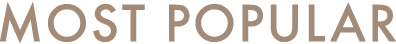lnzyx-iStock
サントリー文化財団が編集する論壇誌『アステイオン』では、いわゆる理系・文系とが相互の研究室を訪問し、その源流を辿ることによって、それぞれの文化の融解を狙う連載企画「超えるのではなく辿る、二つの文化」を掲載している。97号本誌掲載「解く理系に問う文系」のスピンオフとして、研究室の訪問レポートを写真とともに紹介する。第1回目の訪問先は後藤彩子氏(甲南大学理工学部准教授)。

『アステイオン』95号に発表された「学問との再契約(連載企画第1回:超えるのではなく辿る、二つの文化)」 では、筆者の宮野公樹(京都大学准教授)が理系と文系の分裂・共通性について再考しつつ、次のように問うた。
理系と文系の「再契約」は可能なのか。そもそも「理系」と「文系」という二項対立的な思考の「解消」は本当に可能なのかと。実は、私が卒業した総合研究大学院大学(総研大)というあまり耳慣れない大学の、1989年に設立された当初の目標はそこにあった。
あらゆる分野で最先端の研究を行う自然科学と人文社会科学の研究機関が一緒になってそれを実現しようとしたのである。
30年後の今から振り返ってみると、残念ながらその目標は実現できなかったと私は思う。ただ、大学院の時代から「学際的」「国際的」「総合的」という言葉をさんざん聞いてきたおかげで、本企画に参加する機会が訪れた時にどうしても参加したいと思ったのである。
今回の企画では、合わせて3カ所の理系の研究室を訪れた。ここでは、後藤研究室での体験を中心に述べる。
後藤は生物学者であり、長年にわたってアリについて研究していると知るとなぜか妙な感じがした。それは「アリ」が研究対象になりうるとは思っていなかったからである。これまでにラボというと、テレビで見るような白衣を着た博士が危険な化学物質を操るイメージしかなく、アリの研究者とは、機械や化学物質を使って果たしてどのような研究をしているのだろうかと。
しかしそれは、単に私がインドの田舎の学校に通い、理系のラボなどを見たこともなければ、不運にも理系を勉強することもなかったためかもしれない。
実際に後藤研究室を見てみると、それまでの理系のラボのイメージとは大きく違っていた。テレビのようなステレオタイプの博士もいなければ、複雑な機械を使って実験している姿もなかった。