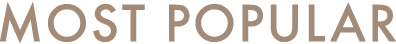いま思い返してみると、不思議なことである。なぜ、私は、そこまで無関心だったのだろうか。なぜ、自身で「理系」の研究に取り組もうと思わなかったのだろうか。おそらく、「理系」の研究の面白さがわからなかった からだろうとは思う。それでは、「理系」の研究の面白さとは何なのか。それは「文系」の研究の面白さとは異なるのか。
本企画では、3人の「理系」の研究者に研究の面白さについて語ってもらった。安藤の研究の面白さは、実はよくわからなかったのだが(『アステイオン』97号を参照)、第1回訪問先の後藤彩子(甲南大学)と第3回訪問先の村田純(サントリー生命科学財団)の研究の面白さは共有できるものであった。
では、その面白さとは何なのか。それは「私と異なるもの」を理解しようとする面白さであったように思う。後藤はアリ、村田は植物である。SFのファーストコンタクトもののような面白さがそこにはあった。
私は、神林長平の『戦闘妖精・雪風』シリーズというSF作品を愛読している。あの作品の面白いところは、人間が作り出した機械を、人間とは全く異なる「未知」の存在であるととらえる点にある。
たとえば、自動車が大好きな人のなかで、自動車を自分と全く異なる「未知」の知性体ととらえている人間がどれほどいるだろうか。車を磨くと、車が喜んでいるように思う人がいるかもしれないが、実は車磨きなど車自身にとっては余計なことにすぎないのだ、などと発想する人がどれぐらいいるだろうか。
『雪風』は、そういう話である。私は、この作品に出会うまで、そんなことは考えたこともなかった。『雪風』は、私がいかに人間中心主義にとらわれていたかを思い知らせてくれた、大切な作品である。
後藤や村田の研究の面白さは、この『雪風』の枠組みで理解できた。ライフ・サイエンスのアルバイトも、この枠組みがあれば面白さが理解できたのかもしれない。私が当時、ライフ・サイエンスの研究をしようと全く思わなかったのは、機械や機械から作られるものを自分とは異なるものと認識していなかったからというのが大きいのではないだろうか。
安藤の研究の面白さがわからなかったのは、私が未だに機械を人間中心主義的にとらえているからなのかもしれない。
よくよく考えてみれば、「私と異なるもの」を理解しようとする面白さは、いわゆる「文系」にも共通しているように思われる。私が死刑を研究してきたのは、私が最も嫌う殺人がどうして制度化されてしまっているのかを知ろうとする試みであったし、私のもう一つの研究対象であるキャバレーは、私が想像もしなかった娯楽文化がどうして社会にあるのか理解しようとする試みであった。
「文系」文化と「理系」文化の融合を模索する場合、この「私と異なるもの」を理解すること、あるいは、「私と異なるもの」を通して「私」を理解しようとすることというのが、重要なポイントになると考える。