【解説】2月2日に最接近し「肉眼で見える」──二度と戻って来ない「緑のZTF彗星」の正体
A COSMIC GIFT OF GREAT PRICE
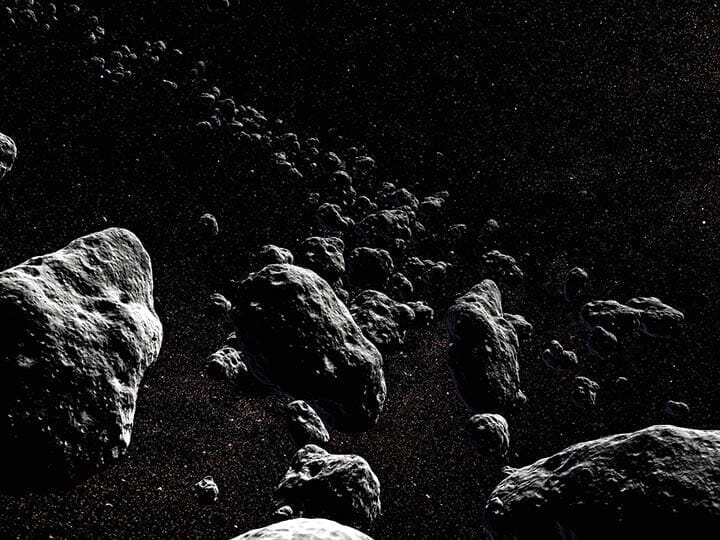
しかし、地上の私たちにとっては顕著な変化がいくつか生じるだろう。例えば、北斗七星を構成する7つの恒星は互いの重力の影響を受けやすいから、5万年もすれば位置が変わり、今のような星座の姿ではなくなるだろう。地球の自転速度は遅くなり、1日が1秒長くなるだろう。ナイアガラの滝は浸食されてただの川になり、北半球には再び氷河期が来ているかもしれない。
アメリカのアリゾナ州には、約5万年前に巨大な隕石が落ちた。そのときのクレーターは今も残っている。直径約1200メートル、深さ約180メートルの巨大な穴だ。そんなものが降ってくる確率は低いが、ゼロではない。だからこそ研究者たちは彗星や小惑星の動きに目を光らせている。
「長周期彗星は太陽系内の小惑星などに比べて極めて大きく、速く動く傾向を持つ。比較的珍しいが、パンチ力は大きい」とアリゾナ大学のマインザーは言う。「しかも、近くに来ないと見えにくい」
衝突の可能性を予測するには、相手を発見して軌道を詳しく調べることが重要だ。「小惑星はただ直進してくるわけではない」と言うのは、NASAで天体防衛チームを率いるケリー・ファストだ。「都心の交通渋滞時と同じで、何かの拍子で2つの物体が同じ空間に居合わすことになれば衝突が起きる」
昨年9月には、NASAの無人探査機ダート(DART)が小惑星ディモルフォスに体当たりする実験を行い、いざとなれば小惑星や彗星の軌道を変更できることを証明した。ただし、十分な距離があるうちに手を打つ必要があることも分かった。仮にZTF彗星が地球に向かっていたとすれば、昨年3月の発見では間に合わなかった(ご心配なく、実際には地球激突コースではない)。
米議会は1995年、NASAに直径1キロ以上の小惑星や彗星その他の地球近傍天体(地球に接近する軌道を持つ天体)の90%を特定するよう指示した。その大きさがあれば6500万年前に恐竜が絶滅したような地球規模の大惨事を引き起こせるからだ。2005年には、標的の規模を「直径140メートル以上」に変更している。
1908年には、シベリアの森林地帯に直径約40メートルの隕石(小惑星も彗星も、大気圏に突入すると隕石と呼ばれる)が落ち、2000平方キロ以上にわたって地上の全てのものをなぎ倒した。今から10年前にも、ロシアのチェリャビンスクに直径約20メートルの隕石が落ちた。このとき集合住宅の窓が吹き飛ぶ様子は携帯電話やドライブレコーダーで撮影された。
NASAは近年、天体の地球衝突に備えるための予算を増やしている。米議会が昨年承認した1億9700万ドルには、ZTFなど世界各地の観測所への助成金が含まれる。おかげで観測件数は飛躍的に増えている。




















