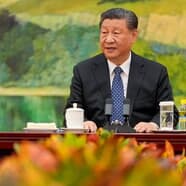「典型的な論者を呼んでも、正直退屈」と講演会で打ち明けられた著述家が、「右でも左でもない」を目指す理由
ネット上では極端な意見が目立つが、そういう人ばかりではない
例えば私が強く共感できたのは、「文春オンライン」に寄せられた「それでもわれわれが『右でも左でもない』をめざすべき理由」という文章だ。
現代の日本では左右のイデオロギー対立がますます深まっており、批判の仕方いかんによってすぐに右・左のレッテルが貼られてしまう。どちらにも属さず「右でも左でもない」という姿勢を取ったとしても、風見鶏だと批判されたりする。
どんな立場にいたとしても、いちいちやりにくく、発言もしづらくなっているということだ。しかし、それでも私たちは「右でも左でもない」という構えを捨ててはいけないと著者は主張する。
興味深いのは、それに関するひとつのトピックだ。
もう四年近く前のことだが、ある編集者に「書き手として、赤旗から聖教新聞まで出られるように」といわれたことがある。そのときはそんなものかと軽く受け流していたが、年々そのことばの重要性を痛感するようになった。現在では完全に座右の銘となっている。(236ページより)
言うまでもなく、両極端なメディアから共に声がかかるくらい独自路線を貫けという意味である。もっと言えば、「右のメディアにも、左のメディアにも出られるようにしろ」ということだ。
私も、これはとても重要だと感じる。
例えば"右認定"された書き手は、右から熱く支持されるいっぽう、左からは攻撃の対象になるだろう。あとから「いや、実はもっと中立的なんだ」と弁解しても、そうした本音は届きにくくなる。
だとすればその書き手が、右の読者にとって心地よく、刺激的なことを書こうという方向に向かっていったとしても不思議ではない。
「右」を「左」に置き換えたとしても同じことが起こるわけだが、いずれにしても健全ではない。特定の立場からしか声がかからなくなることは大きなリスクを伴うし、自由の喪失にもつながる。
だから著者は書き手として、中間を目指すべきだと訴えるのである。
さまざまな分断の隘路(あいろ)に陥らず、書き手として自由にやっていくためには、どうすればよいだろうか。それは、あらゆる点でバランスを図り、やはり「赤旗」からも「聖教新聞」からも声がかかるように、独自路線を追求する以外にない。
そうすることで、さまざまな弊害――凡庸な戦前批判または戦前美化を繰り返すことや、ポリティカル・コレクトネスなど大義名分を振り回すこと、また学術用語をちりばめて政治運動をことごとく衒学(げんがく)的に例証することなど――から逃れられる。(240ページより)
「現在が分断にもとづく動員の時代であることは事実なのだから、独自路線を突っ走ることこそ滅びにつながるのではないか」という考え方もあるかもしれない。しかし、そこにこそ本当の希望があるのだ。