新型肺炎で中国の調査報道は蘇るか
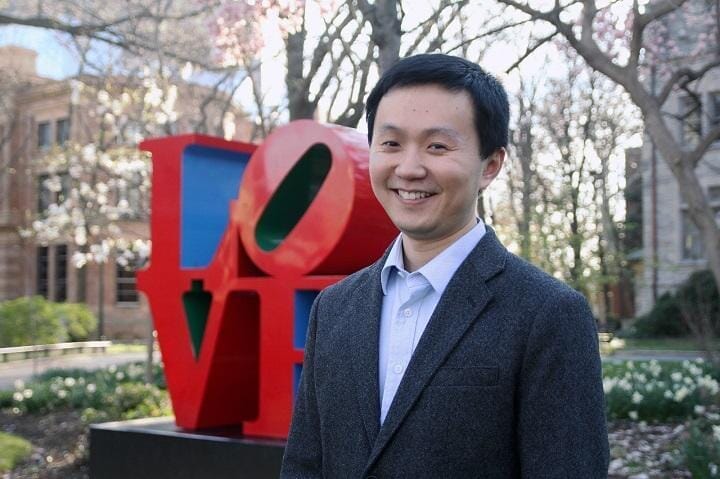
2つ目の理由は政治と関係している。習近平が共産党総書記・国家主席になった後、特にニュース報道の面で締め付けが非常に強まったことにより、記事を書いても発表できないという事が増えた。であれば業界に残る意味がないと考える人も多かった。
自分が在籍していた南方週末も同じだった。2010年に実際に働き始めてみると学生の頃あこがれていた姿はすでにそこにはなく、しかも状況は日増しに悪くなっていった。12年は政権の変わり目にあたる年だったことから共産党中央宣伝部の記事への介入が特別多く、南方週末も指示を受けて実際にたくさんの記事を削除させられた。南方週末は当局にとって明らかに「出る杭」で、以前は許される言論の空間がもっとも大きかったが、それが故に最も強い圧力を受けていた。
多くの関心を集めた13年新年号の社説差し換え事件(注:掲載予定だった社説が広東省の共産党委宣伝部の指示により、編集部を無視する形で書き換えられて発表されたことに編集側が反発。市民や他のメディアを巻き込んだ大規模な抗議活動に発展した事件)は、積もり積もった圧力とそれに対する内部の抵抗の相克が表出したものだったと言えるだろう。その後も状況は良くなることはなく、ちょうどアメリカで博士号を取る事を考えていた私は南方週末を離れることを選んだ。
──しかし今般の新型肺炎に関する報道では「財新」や「三聯生活週刊」などの記者が現場に入りその様子を伝えるなど、久しぶりに存在感を示している。調査報道の社会に対する意義が見直され、あなたの言う「黄金時代」は戻ってくるのだろうか?
今回これだけの質の高い報道ができていることはいわば嬉しい誤算だった。例えば02~03年のSARS報道の際も多くの良質な記事を発信していた雑誌「財新」は今回も非常に頑張っていて、実際自分の周りでも応援の意味をこめて有料購読を始めたという人も多い。他にもいくつも素晴らしい報道を行っているメディアは存在するし、必要以上に悲観的にならなくてよいと思う。
とはいえ当然、すべてのメディアの収入が突然大幅に伸びるはずもない。そして政治的な圧力の強さも依然変わらない。中国共産党は政治的な意見の統一と無謬性を最優先にメディアを指導してきた。今回のような報道の必要性に気づいた人々が声をあげ、政府の方向性が変わらない限り、残された生存空間が広がる事はないだろう。
他国とは違った形ではあるが、共産党系のメディアも調査報道と親和性がないわけではない。単なるプロパガンダ機関だと思う人も多いかもしれないが、実は党系メディアは全国各地に拠点を持ち当地の事情にも詳しいので、本来は中央の「眼」として地方行政を監視し、指導する役割も担っている。だが今回に限って言えばせいぜいSNS上で「武漢加油(がんばれ武漢)」などという投稿をするのが関の山で、その役割を果たしているとは言えないのが残念だ。
<常に抑圧されてきた調査報道がなぜ政府から今回に限ってあまり規制されず「大目に見られている」ように見えるのか、その正確な理由はわからない。今回活躍しているメディアは政府系の中で比較的リベラルな歴史を持つものや民間であっても政府との関係の深い老舗が主だ。SARSの際も最終的に政府が一定程度こうした報道の意義を認めた経験を踏まえつつ、慎重に「空気」を読みながら報道を行っていると思われる。
中央政府は内心もっとコントロールしやすい党直轄の新聞などにやらせたいはずだ。だが、SNSでバズることばかり考えている党系メディアからは既に調査報道のノウハウは消失していて任せられず、結果として存在感を示したい伝統メディアと利害が一致し、許容されているのでは――と考える。>




















