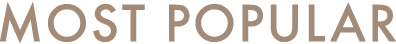beyhanyazar-iStock
新型コロナウイルスによるパンデミックが世界を覆うなか、疫病が蔓延し封鎖された都市に生きる人々を描いたアルベール・カミュの小説『ペスト』(1947)が世界中で再注目された。
カミュは当時フランス領だった北アフリカのアルジェリアに生まれ、『ペスト』の舞台も西部の主要都市オランである。
一方、現在この街に暮らすジャーナリストのカメル・ダーウドが初の長編小説『ムルソー、再捜査』を首都アルジェで出版したのが2013年。
翌年フランス版が発売されるや大評判となり、世界各国で翻訳が相次いだ。本作は、カミュのもう一つの代表作『異邦人』(1942)を下敷きに、「太陽が眩しかったせい」で主人公ムルソーに射殺された名もなきアラブ人の背景を問い、その弟を語り手として創造したものだ(邦題は『もうひとつの「異邦人」』)。
歴史を新たな視点で振り返るのは文学の役割の一つである。『ペスト』の背景にはドイツ占領下を生きたフランス人の経験があり、『ムルソー、再捜査』はフランス支配下で封殺されたアルジェリア人の声を甦らせる。
同時に『ペスト』が疫禍に苦しむ人々の連帯と勇気を描いた作品として共感をもって読み返されているように、文学は常に「いま」を主題として立ち現れる。
『ムルソー、再捜査』も、世界中のカミュの読者に『異邦人』の死角を突いたポストコロニアル文学の傑作として歓迎されたものの、よくよく読んでみれば、独立後のアルジェリア社会の欺瞞を告発する作品である。
その批判の矛先は、過ぎ去ったフランスの植民地支配よりも、むしろアルジェリアの権威主義体制とイスラーム主義の蔓延といった「いま」に向けられているのだ。
カメル・ダーウドが影響を受けた作家の一人として名を挙げるブアレム・サンサールは、自らの生まれ育った社会を手厳しく批判する作家の急先鋒として知られている。その極みともいえる作品がジョージ・オーウェルの『1984』を模したディストピア小説『2084 世界の終わり』(2015)だ。
唯一神ヨラーを奉じるアビスタンという架空の神権主義国家を語る本作は、同年にミシェル・ウェルベックが発表した『服従』(イスラーム主義者がフランスの政権を奪取するという近未来小説)とともに世間の話題をさらった。
図らずもパリではシャルリー・エブド社が襲撃されたのみならず市街地で無差別テロが多くの命を奪い、イラクやシリアでは自称「イスラーム国」が猖獗(しようけつ)を極めていた。