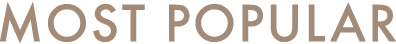久板栄二郎『女性祭』(1947年、中央社)表紙 撮影:小川佐和子
この9月に神奈川芸術劇場で長塚圭史演出の『夜の女たち』というミュージカルを観劇した。溝口健二監督の同名作品(1948年、松竹)のミュージカル化である。
戦後の大阪・釜ヶ崎で、男への復讐のために街娼へと身を落としていく房子、破れかぶれの日々を送るなかで男に性病をうつされ死産する夏子、家出をして底辺まで堕落しかける久美子という3人の女性を中心に、闇の女性たちの分断と連帯を描いた作品である。
映画では房子を田中絹代、夏子を高杉早苗、久美子を角田富江が演じ、ミュージカルではそれぞれ江口のりこ、前田敦子、伊原六花が好演した。
久板栄二郎の原作シナリオ『女性祭』(1947年、中央社)では、著者自身が次のように解説している。
原作では最後に房子が病気で息絶えるのに対し、映画では明日を生きる女性たちをマリア像が見守るという象徴的なラスト・ショットに変更された。映画化に際してこうした多少の改変はなされているが、久板の意図は概ね映画の主軸となっている。
なぜこの作品を現代に甦らせるのか、その真意がよくつかめないまま、半ば怖いもの見たさの好奇心で劇場に足を運んだ。
怖いもの見たさとは、溝口の映画を見た者ならおそらく誰しも感じるはずだが、オリジナルの映画がおよそミュージカルというジャンルにはそぐわない壮絶なリアリズムを呈しているからだ。
寄りのショットによる映画女優たちの表情の凄みが舞台では表せないし、セットの閉鎖的な心理空間やロケーション撮影で捉えた裏大阪という土地がもたらす情念も、現代の清潔なステージでは失われてしまう。
プログラムノートには歌でしか伝わらないことがあると書いてはあったが、調子の整った美しい歌声や華やかなダンスが紡ぎ出す物語には絶望の強度が薄れてしまっていた。
むしろ江口のりこの生のセリフのほうが、胸に刺さるものがあった。ミュージカル専門ではない役者たちにストレートプレイではなく歌と踊りで勝負させたという目論見が果たして功を奏したのかどうか、終幕まで疑念が残った。
とはいえ、単にオリジナル映画の礼賛をするつもりはない。それに『女性祭』と銘打たれている久板の原作シナリオまでさかのぼると、華美に着飾る舞台女優とダンサーたちは、敗戦を日本女性の解放と捉える作者本来の意図を汲み取ったとも言える。